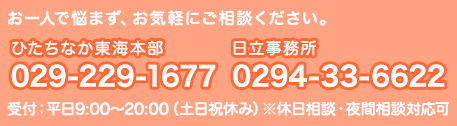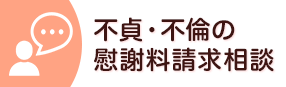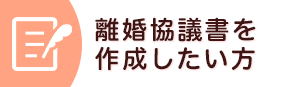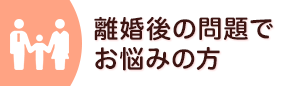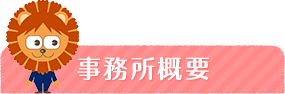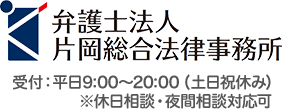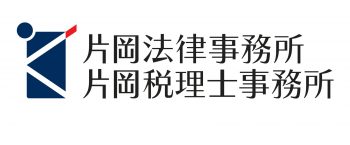離婚時の財産分与に関する税金
1. 財産分与とは?基本と税金の関係
離婚の際には、夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分け合う「財産分与」が行われます。この財産分与は、離婚後の生活設計において非常に重要な手続きですが、同時に税金の問題も関わってくるため注意が必要です。
財産分与の定義と対象財産
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた共有財産を、離婚に際してそれぞれの貢献度に応じて分配することを指します。対象となる財産(共有財産)には、現金、預貯金、不動産、自動車、株式、退職金、年金などがあります。名義が夫婦のどちらか一方でも、実質的に夫婦の協力によって得られた財産であれば財産分与の対象となります。
財産分与には、以下の3つの要素が含まれると考えられています。
- 清算的財産分与: 夫婦の共有財産を公平に清算する要素。
- 扶養的財産分与: 離婚により生活が困窮する一方を扶養する要素。
- 慰謝料的財産分与: 離婚の原因を作った側が支払う慰謝料の要素。
財産分与に税金がかかるケースとかからないケース
財産分与においては、原則として財産を受け取る側にも、渡す側にも贈与税や所得税はかかりません。これは、財産分与が他方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための給付と考えられるためです。
しかし、以下のような特定のケースでは税金が発生する可能性があります。
- 受け取る側にかかる可能性のある税金:
- 贈与税: 分与額が過大である場合や偽装離婚とみなされる場合。
- 不動産取得税: 不動産を取得した場合(ただし、清算的財産分与であれば非課税となる場合が多い)。
- 渡す側にかかる可能性のある税金:
- 譲渡所得税: 不動産や株式など、値上がり益の生じる財産を分与した場合。
これらの税金については、次項以降で詳しく解説します。
2. 財産分与を受ける側の税金(贈与税・所得税)
財産分与で財産を受け取る側は、原則として贈与税や所得税の心配は不要です。これは、財産分与が夫婦の共有財産の清算や、離婚後の生活を支えるためのものと考えられるため、税務上も贈与や所得とは異なる扱いを受けるからです。
原則として贈与税はかからないが、例外がある
通常の財産分与であれば、受け取った財産に対して贈与税が課されることはありません。しかし、例外的に贈与税が課税されるケースが存在します。それは主に以下の2つの場合です。
分与された財産の額が過大な場合
財産分与として受け取った額が、社会通念上相当と認められる範囲を「多すぎる」と判断される場合、その過大な部分について贈与税が課されることがあります。
離婚が贈与税や相続税逃れのための偽装であると認められる場合
税金の支払いを免れる目的で形式的に離婚したと税務署に判断された場合には、分与された財産全体に贈与税が課される可能性があります。
このようなリスクを避けるため、財産分与の合意内容を離婚協議書などの書面に明確に残しておくことが重要です。
財産分与を現金で受け取る場合の注意点
財産分与を現金で受け取る場合、その現金自体に贈与税がかかることは原則ありません。また、所得税についても、一時所得などとして課税されることは基本的にありません。例えば、離婚の慰謝料として現金を受け取った場合も、心身に加えられた損害に対する賠償金として非課税とされています。
ただし、高額な現金を一度に受け取る場合、税務署から資金の出所について問い合わせが来る可能性もゼロではありません。財産分与によるものであることを証明できる離婚協議書などを保管しておくことが推奨されます。
3. 財産分与をする側の税金(譲渡所得税)
財産分与で財産を渡す側は、分与する財産の種類によって「譲渡所得税」が課税される場合があります。特に不動産や株式など、取得した時よりも価値が上がっている可能性のある財産を分与する際には注意が必要です。
不動産や株式を分与する際に発生する税金
現金や預貯金をそのまま分与する場合、渡す側に税金はかかりません。しかし、土地、建物、株式などの資産を財産分与する場合、その資産を分与時の「時価」で相手に譲渡したものとみなされることがあります。特に、慰謝料や扶養料の支払いに代えて不動産などを渡す場合(代物弁済)は、この「みなし譲渡」に該当します。
そして、その資産の取得時の価額(取得費)よりも分与時の時価が高い場合には、その差額(値上がり益)が譲渡所得として認識され、譲渡所得税(所得税および住民税)の課税対象となります。逆に、清算的財産分与として、夫婦の共有財産を貢献度に応じて分ける場合は、原則として譲渡所得税は課税されません。
譲渡所得税の計算方法(取得費・譲渡価格)
譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。 譲渡所得 = 収入金額(譲渡価格) – (取得費 + 譲渡費用)
- 収入金額(譲渡価格): 財産分与の場合は、分与時の時価となります。
- 取得費: その資産を購入した時の代金や手数料などです。
この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率で所得税と住民税が課税されます。
- 短期譲渡所得: 所有期間が5年以下のもの → 税率 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
- 長期譲渡所得: 所有期間が5年超のもの → 税率 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) ※税率は2025年6月現在のものです。復興特別所得税を含みます。
節税対策としての特別控除
譲渡所得税には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という重要な制度があります。自分が住んでいる家屋やその敷地を財産分与する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
- ポイント: 離婚が成立した後の財産分与であれば、元配偶者は「特別な関係にある者」に該当しないため、この特例の適用が可能です。離婚成立前の分与では適用できない点に注意が必要です。
4. 不動産の財産分与に関する税金と注意点
不動産は財産分与の中でも特に高額になりやすく、税金関係も複雑になりがちです。
不動産取得税
不動産を取得した側には、原則として不動産取得税が課税されます。ただし、財産分与が夫婦の共有財産の清算として行われたと認められる範囲内であれば、課税されない場合があります。
登録免許税
不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際には、登録免許税(固定資産税評価額の2%)が必要です。
住宅ローンが残っている場合
誰がローンを支払い続けるか、金融機関の承諾が得られるかなど、法務・税務だけでなく金融機関との調整も必要になるため、専門家への相談が不可欠です。
共有名義の不動産を分与する際
一方の持分をもう一方に移転する形になり、移転する持分に対して各種税金がかかります。将来のトラブルを避けるためにも、分与方法や条件を離婚協議書に明確に記載しておくことが重要です。
5. 財産分与の税金を抑える方法
財産分与に伴う税金は、いくつかの工夫や制度の活用によって負担を軽減できる可能性があります。
夫婦間での財産分与契約書の活用
分与が清算的要素に基づくものであることなどを明記しておくことで、贈与税などの指摘を受けるリスクを低減できます。
特例や控除を活用する方法
「居住用財産の3,000万円の特別控除」などを適用するためには、離婚成立後に財産分与を行うなどのタイミングが重要になります。
最適なタイミングで分与する工夫
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで大きく変わります。どのタイミングで分与するのが最も有利か、専門家とシミュレーションを行うことが有効です。
6. 弁護士・税理士の必要性
離婚時の財産分与は、法律や税金といった専門的な知識が不可欠となる複雑な問題です。
- 弁護士: 離婚協議全体の進め方、交渉、法的に有効な書面作成、法的手続きの代理など、法的な側面から幅広くサポートします。
- 税理士: 税金の計算、各種特例の適用の可否判断、節税に関する具体的なアドバイス、税務申告など、税務面を専門的にサポートします。
多くの場合、弁護士と税理士が連携して対応することで、法務・税務の両面から最適な解決策を見つけることができます。
7. 当事務所のサポート
当事務所では、離婚問題に精通した弁護士が、財産分与に関するあらゆるご相談に対応しております。
- 交渉・調停・訴訟の代理
- 離婚協議書・財産分与契約書の作成支援
- 税金に関するアドバイスと税理士連携
- 不動産の名義変更等の手続きサポート(司法書士連携)
お客様一人ひとりの状況を詳細にお伺し、法的な観点だけでなく、税務面も考慮に入れた上で、最善の解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。