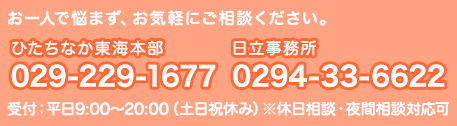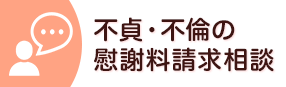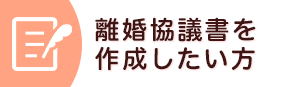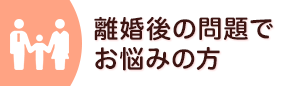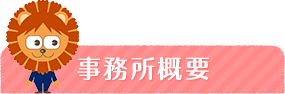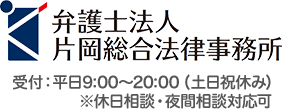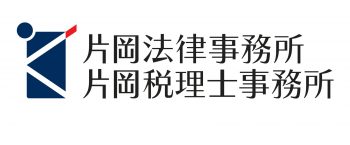年金分割の知っておくべき基本、手続き、注意点について弁護士が解説
離婚を検討される際、財産分与と並んで重要なのが「年金分割」です。これは、婚姻期間中に夫婦が共に築き上げた厚生年金や共済年金の保険料納付実績を分け合う制度です。将来の生活設計に大きく影響するため、正しい理解が不可欠です。
長年寄り添ってきた夫婦が、それぞれの未来へと歩み出す熟年離婚。人生の大きな転換期を迎えるにあたり、経済的な問題は避けて通れません。特に、老後の生活を支える柱となる年金については、その仕組みをしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事では、年金分割制度の基本的な仕組みから手続き、注意点、そして専門家である弁護士に相談するメリットまで解説します。
1. 年金分割制度とは?
年金分割とは、離婚の際に、婚姻期間中に夫婦が協力して積み立ててきた厚生年金保険料の納付実績を、より多く納めてきた側から少ない側へと分け与える制度です。多くの場合、長年にわたり会社員として勤務していた夫から、専業主婦やパートタイムで働いていた妻へと分割されるケースが多く見られます。
この制度を活用することで、年金を受け取る側の将来の年金額が増加し、経済的な自立を支えることが期待できます。一方で、年金を分割する側は、将来受け取れる年金額が減少することになります。
対象となる年金と期間
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金や共済年金といった被用者年金の保険料納付実績です。国民年金(基礎年金)や国民年金基金は分割の対象外です。また、企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金など)も原則として対象外ですが、過去の厚生年金基金の加入期間の一部(代行部分)は分割対象に含まれる場合がありますので確認が必要です。
分割の割合
年金分割の割合は、原則として上限が2分の1(50%)と定められています。当事者間で自由に合意できるかのように思われるかもしれませんが、実際には50%以外の合意が成立することは極めて稀です。その理由は、按分割合に関する争いが生じた場合、家庭裁判所は特別な事情がない限り、ほぼ例外なく50%を適用するからです。このため、調停においても50%が一般的な取り決めとして扱われます。
請求期限
離婚後の年金分割請求には、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内という期限が設けられています。この期間を過ぎてしまうと、原則として請求することができなくなりますので注意が必要です。
2. 年金分割の2つの方法「合意分割」と「3号分割」
年金分割には主に「合意分割」と「3号分割」の2つの種類が存在します。
合意分割
婚姻期間全体の厚生年金保険料納付記録を対象とし、夫婦間の話し合いによって分割割合を決定するものです。
分割対象
婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた厚生年金の標準報酬総額。
分割割合
夫婦間の合意または裁判所の決定に基づき、最大50%の範囲で定めます。実務上は、特別な事情がない限り50%となります。
3号分割
平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者(主に専業主婦や配偶者の扶養に入っていた方)であった期間の厚生年金保険料納付記録について、請求に基づいて一律2分の1の割合で分割されるものです。
被保険者の定義
- 第2号被保険者:主に会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
分割の自動性と割合
相手の同意は不要で、請求により自動的に分割されます。分割割合は常に2分の1です。
対象期間
平成20年(2008年)4月以降の第3号被保険者期間のみが対象となります。
どちらを選ぶべきか?
一般的に、婚姻期間全体を対象とする合意分割の方が、年金分割を求める側にとって有利となることが多いです。しかし、ご自身の状況に適しているかは個々の状況によって異なりますので、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
3. 年金分割の手続きの流れ
ステップ1:年金分割のための情報通知書の取得
年金分割を行う際には、まず「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で取得します。 この書類を入手するためには、以下の書類が必要です。
- 年金分割の情報提供請求書(年金事務所で入手可能)
- 戸籍謄本(発行から6か月以内のもの)
- 外国国籍の方は、婚姻関係を証明できる公的な書類(婚姻証明書など)とその日本語訳
- 身分証明書:
- 【1点で可】マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(写真付きのもの)
- 【2点必要】健康保険証、公共料金の領収書、預金通帳など(写真なしのもの)
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など、基礎年金番号がわかる書類
- 印鑑(認印)
ステップ2:年金分割の割合の決定(夫婦間の協議と合意書の作成)
夫婦間の協議で分割の割合について話し合い、合意内容を公正証書などにまとめます。合意が難しい場合は、家庭裁判所へ調停または審判を申し立てます。
ステップ3:年金事務所への請求
年金分割の割合を定めた後、年金事務所へ請求手続きを行います。これには以下のいずれかの書類が必要です。
- 年金分割の合意に関する公正証書を作成した場合:公正証書の謄本または抄本
- 家庭裁判所で調停が成立した場合:調停調書の謄本または抄本
- 審判または判決が確定した場合:審判書(または判決書)の謄本または抄本と確定証明書
これらの手続きの後、離婚成立日の翌日から2年以内に年金事務所に届け出る必要があります。自動的には分割されませんのでご注意ください。
〈請求時に共通で必要な主な書類〉
- 改定請求書(年金事務所で入手可能)
- 当事者それぞれの戸籍謄本(または抄本)や住民票など(離婚日の記載があり、請求日の前6か月以内に発行されたもの)
- 身分証明書(現住所が分かるもの)
手続きの詳細は年金事務所にご確認ください。
4. 年金分割で考慮すべきポイントと注意点
請求期限は離婚後2年以内!
この期限は非常に重要です。
分割は「記録」であり現金給付ではない
分割されるのは将来の年金額を計算するための保険料納付記録であり、即座に金銭を受け取れるわけではありません。
対象者
専業主婦だけでなく共働き夫婦も対象です。
分割対象となる年金とならない年金の違い
年金分割の対象は厚生年金(共済年金)部分のみです。国民年金(基礎年金)部分は分割されないため、分割後の自身の年金がどのようになるか、全体像を正しく理解することが重要です。
50歳以上の方は年金見込額の試算が可能
日本年金機構の「ねんきんネット」や年金事務所の窓口で、より具体的な年金見込額を試算できます。
5. 年金分割に関する実務上の課題
制度理解の難しさ
日本の年金制度が複雑であるため、具体的に将来の年金にどのような影響があるのかを理解するのは難しいことです。そのため、年金制度に精通した弁護士のような専門家でなければ、正確に判断するのは難しいのが実情です。
相手方との協議の難しさ
離婚という状況下での不信感や、制度への誤解(例:「結婚前の年金も含まれる」など)から、50%の分割に相手方が納得できず、話し合いが進まないことが多く見受けられます。
年金分割を進める上でのハードル
- 相手が分割の合意に応じないと(合意分割は)成立しない
- 感情的な対立により冷静な話し合いが難しい
- 公正証書の作成や裁判所の手続きに時間と手間がかかる
年金分割をスムーズに進めるためには、専門家のサポートを受けることが有効です。
6. 弁護士への相談の利点と当事務所のサポート
専門家への相談の重要性
年金分割は将来の生活を左右する重要な問題です。制度を正しく理解し、公証役場や家庭裁判所での手続きを適切に進めるためには、実務経験や専門的な知識が必要です。
弁護士への依頼の利点
効果的な交渉
専門家が間に入ることで、冷静な対話が実現し、法に基づいた適切な解決を目指せます。
全体的な手続きもお任せ
財産分与や慰謝料など、離婚に伴う他の問題も含めて、調停から裁判まで幅広くサポートを受けられます。
法律相談
離婚に関する正式な法律相談や代理交渉は、法律で弁護士にしか認められていません。
当事務所のサポート
当事務所では、すぐに調停を申し立てるのではなく、まず弁護士が代理人として相手方と交渉する「代理交渉」から始めることを提案しています。これにより、時間や労力の負担を軽減し、早期解決を目指します。交渉で合意できない場合は、離婚調停の申立てへと移行し、適切な条件での成立を目指してサポートします。
当事務所の弁護士は、年金分割だけでなく財産分与などの関連事項も包括的にサポートいたします。オンライン相談も実施しております。
おわりに
この記事が、熟年離婚を検討されている方にとって有益な情報となれば幸いです。法律的な問題を適切に扱うためには、専門家の力が不可欠です。
当事務所では、年金分割に関するご相談を承っております。ご夫婦の状況やご希望を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。